

ファクタリング会社を選ぶ基準として大事なことは、手数料や費用の負担金額とファクタリング会社の信頼性になります。
中には本来は掛からない消費税や高額な手数料を請求してくる悪徳業者も存在するので注意が必要です。
そこで本記事では、ファクタリングに掛かる手数料の相場や内訳を詳しく解説いたします。
目次
ファクタリングの種類と手数料の相場

ファクタリングには次の4つの種類があります。
ファクタリングの種類によって、ファクタリング会社が負うリスクも異なるので、利用するファクタリングの種類によって手数料も異なることになります。
- 一括ファクタリング
- 医療ファクタリング
- 国際ファクタリング
- 保証ファクタリング
まずは4つのファクタリングの手数料相場についてご紹介していきます。
一括ファクタリング
一括ファクタリングとは、納入企業が保有する売掛債権を金融機関が一括で買い取り、納入企業へ買取代金を支払うサービスになります。
一般的な買取ファクタリングに加えて、一括ファクタリングは売掛債権の決済事務を一括して引き受けるので納入企業の事務コストを大幅に低減できるという点がメリットです。
メガバンクなどが行なっていたサービスですが、今は一般的な「買取ファクタリング」や「でんさい」が主流となっているので一括ファクタリングを取り扱っている金融機関はほとんどありません。
一括ファクタリングの手数料相場
一括ファクタリングは基本的に銀行が提供するサービスで、3社間ファクタリングで行われることから、手数料は1.0〜5.0%程度と比較的安価になっています。
医療ファクタリング
医療ファクタリングとは、「病院が保有する診療報酬債権」や「介護施設が保有する介護報酬債権」を対象としたファクタリングの名称です。
これらの医療報酬は発生から現金化するまで最大で3ヶ月程度の時間がかかります。
この資金ギャップを埋めるのが医療ファクタリングです。
医療ファクタリングを利用すれば、医療報酬を請求後すぐに資金化できるので、3ヶ月程度の資金ギャップを半分程度に縮めることができます。
医療ファクタリングの手数料相場
債務者は保険組合や国保連などですので、支払いに対する確実性が高く、3社間ファクタリングで行われます。
ファクタリング会社にとっては非常にリスクが低いため、1.0〜4.0%程度の安価な手数料でファクタリングできるのが特徴です。
国際ファクタリング
国際ファクタリングとは、日本のファクタリング会社と海外のファクタリング会社が連携し、輸出業者の債権の保証を受ける仕組みです。
輸出業者はファクタリング会社の保証によって、確実に代金を受け取ることができるので、安心して貿易ができます。
従来の信用状の発行などによる貿易の仕組みよりも圧倒的に早く簡単に債権の保証を得られるので、国際取引の円滑化に寄与します。
国際ファクタリングの手数料相場
国際ファクタリングの手数料は1ヶ月あたり、0.7〜2.0%程度となっています。
従来の信用状の発行にかかる手数料が年0.5〜1.0%程度であることと比較すると、国際ファクタリングの方が手数料は高くなります。
保証ファクタリング
保証ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社が保証するものです。
万が一、売掛債権がデフォルト(支払われない)した場合には、保証ファクタリングを利用しておくことで、ファクタリング会社から代金を支払ってもらうことができます。
業況が心配な企業や、初めて取引する企業の売掛債権に対して保証ファクタリングを利用することによって確実に代金を回収できるので安心です。
保証ファクタリングの手数料相場
保証ファクタリングの手数料は売掛債権のリスクによって異なるものの、0.5%〜3.0%程度が相場となっています。
中小企業が利用するファクタリングの手数料の相場
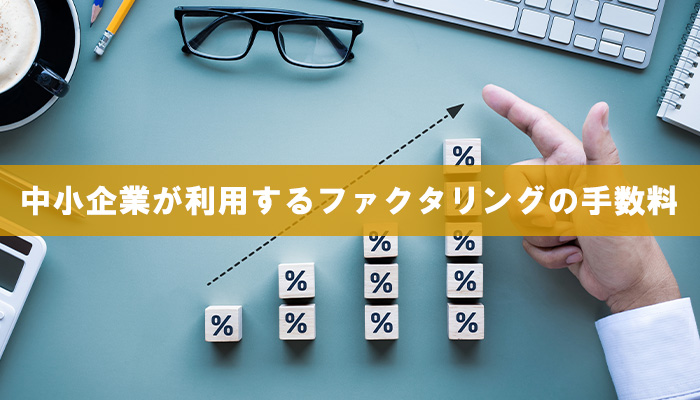
中小の事業者の方々が最もよく利用するファクタリングが「買取ファクタリング」です。
買取ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があり、2社間と3社間では手数料が大きく異なります。
それぞれの手数料相場と、なぜ2社間と3社間で手数料が異なるのか、詳しく見ていきましょう。
2社間ファクタリングの手数料相場は10〜20%
2社間ファクタリングの手数料相場は10〜20%程度が相場となっています。
2社間ファクタリングとは、納入企業とファクタリング会社の2社だけで契約する取引です。
2社だけの取引においては次のようなリスクがあります。
- 売掛債権期日にファクタリング会社へ代金を支払わない
- 売掛債権を二重譲渡する
- 架空の売掛債権を譲渡する
2社間ファクタリングでは、納入企業が売掛先企業から入金された代金をファクタリング会社へ送金します。
この際に、納入企業がファクタリング会社に対して代金を支払わないというリスクがあります。
また、すでに他のファクタリング会社に対して売却済の売掛債権を別のファクタリング会社へ二重譲渡するリスクも否定できません。
さらに、そもそも存在しない架空の売掛債権をファクタリング会社へ売却するリスクもあるでしょう。
このように、売掛先企業が取引に関与しない2社間ファクタリングにおいては、売掛債権そのもののリスクに加えて、納入企業のリスクも存在します。
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングよりもリスクが高いため、10〜20%程度という非常に高い手数料が設定されるのが一般的です。
3社間ファクタリングの手数料相場は1.0〜9.0%
3社間ファクタリングの手数料相場は1.0〜9.0%と2社間ファクタリングと比較して安価です。
3社間ファクタリングは納入企業・売掛先企業・ファクタリング会社の3社での取引になります。
ファクタリング契約の際には、ファクタリング会社と売掛先企業が直接やりとりを行い、売掛先企業がファクタリングに同意をした上でファクタリング契約を締結します。
そして、売掛債権の期日になると、売掛先企業が直接ファクタリング会社へ代金を支払います。
そのため2社間ファクタリングには存在した次のリスクが3社間ファクタリングにはありません。
- 納入企業による代金持ち逃げのリスクがない
- 二重譲渡の心配がない
- 架空の売掛債権の心配がない
3社間ファクタリングでは納入企業のリスクを加味する必要がないので、2社間ファクタリングよりも低い手数料で利用することができます。
ただし、売掛先企業の同意を取得する時間がかかるので、3社間ファクタリングでは申込から資金化までに1週間以上の時間がかかってしまうことも珍しくありません。
ファクタリングの手数料は売掛債権の信用で決まる

ファクタリングの手数料は売掛債権のデフォルトリスクに対するリスクプレミアムとして設定されます。(※リスクプレミアムとは、「リスクのある資産の収益率」から「無リスク資産の収益率」を引いた差となります。)
そのため、売掛債権のリスクに応じてファクタリングの手数料は異なります。
売掛債権の信用度を構成するのは次の5つの要素です。
- 売掛先企業の規模
- 売掛先企業の業況
- 売掛債権の金額
- 売掛債権の期間
- 2社間ファクタリングでは自社に信用も重要
それぞれの要素が具体的にどのように手数料に影響するのか、詳しく解説していきます。
売掛先企業の規模
売掛先企業の規模が大きければ「売掛債権が期日通りに支払われる可能性が高い」と判断できるので、ファクタリング手数料も低くなります。
反対に売掛先企業の規模が小さければ、売掛債権が期日通りに支払われるかどうかが懸念されます。
ファクタリング会社にとってリスクが高くなるので、規模の大きな企業の売掛債権よりも手数料が高くなりやすい傾向にあります。
そのため、ほとんどの企業が法人または公共団体に対する売掛債権しか買取に対応しておらず、個人事業主に対する売掛債権は買取対象外となっているのが一般的です。
売掛先企業の業況
売掛先企業の業況はファクタリングの手数料を決定する最も重要な要素と言っても過言ではありません。
売掛先企業の業況に問題がなければ、売掛債権の代金支払いには問題ないと判断でき、手数料はそこまで高くなることはないでしょう。
一方、売掛先企業が赤字や債務超過などの場合には、売掛債権の代金支払いにも疑問が生じるため、手数料が高く設定される傾向にあります。
あまりにも業況に問題がある場合には、ファクタリングを断られてしまう可能性もあるでしょう。
売掛債権の金額
売掛債権の金額が大きい方が手数料が低くなる傾向があります。
売掛債権の金額が大きければ、例え手数料率が低くてもファクタリング会社は収益を確保することができるためです。
例えば、100万円の売掛債権のファクタリングに手数料20%を設定した場合、ファクタリング会社の手数料収入は20万円です。
他方、1,000万円の売掛債権のファクタリング手数料が10%の場合には、ファクタリング会社には100万円の手数料収入が入ります。
このように、売掛債権の金額が大きくなれば、手数料率は低くなる傾向にあります。
複数の売掛債権を別々にファクタリングするよりも、まとめて大きな金額にしてファクタリングした方が手数料は低くなるため、ファクタリングの際には、できる限りまとめて売却することを意識しましょう。
売掛債権の期間
売掛債権の支払期日までの期間が長ければ手数料は高くなりますし、短ければ手数料は低くなる傾向にあります。
支払期日までの期間が長い方が、期日通りに支払いが行われないリスクが高くなるためです。
経営は常に動いているため、支払期日までの期間が長ければ期日までに大きな経営上の危機に晒されるリスクがあります。
一方、期日までの期間が短ければ経営上の危機に晒されるリスクは低いと言えます。
手数料をできる限り引き下げたいのであれば、期日までの期間が短い売掛債権をファクタリングした方がよいでしょう。
2社間ファクタリングでは自社の信用も重要
2社間ファクタリングにおいては納入企業である自社の信用も重視されます。
自社の業況が悪いと、売掛債権代金の持ち逃げや二重譲渡や架空の売掛債権を計上するリスクが高くなるためです。
そのため、自社の業況があまりにも悪いとファクタリングを断られてしまう可能性もあります。
ファクタリング会社にとって「この会社は信用できる」と判断されることが重要です。
そのため、同じファクタリング会社と継続的に取引を行い、ファクタリング会社からの信頼を蓄積していくことで、2回目以降の利用の際に2社間ファクタリングの手数料が下がる可能性があります。
ファクタリングで発生する手数料の内訳

ファクタリングの手数料には、「ファクタリングにかかる全ての経費が含まれている」というのが基本的な考えです。
そのため、一概に手数料と言っても、手数料の全てが売掛債権のリスクプレミアムというわけではなく、ファクタリング業務に当たって発生する以下のような必要経費も含まれています。
- 掛け目
- 買取手数料
- 債権譲渡登記費用
- 印紙代
- 振込手数料
- 交通費
それぞれ、どのような費用で、いくらくらいかかるものなのか、詳しく解説していきます。
掛け目
掛け目とはファクタリングの買取率です。
ファクタリングでは売掛債権の額面金額全てを買い取ってくれるわけではありません。
一般的に額面の75~90%の金額を買い取り、控除された分は売掛債権を回収できた際に返却される仕組みとなっています。
ファクタリングの際には掛け目によって買取額が減額されるので、掛け目による減額分もファクタリングの際に発生する手数料の一部だと言えるでしょう。
買取手数料
ファクタリングの際にかかる手数料で、この分がファクタリング会社の収益になります。
ファクタリングでは、売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が負います。
この回収リスクに対するリスクプレミアムとして設定され、回収リスクの高い売掛債権であれば、手数料も高くなる傾向にあります。
債権譲渡登記費用
2社間ファクタリングでは債権譲渡登記という登記を行うことがあります。
債権譲渡登記とは、債権を譲渡したことを登記するもので、これによって第3者に対して「この債権はすでに当社が譲渡を受けたものだ」と主張することができるので、二重譲渡を防ぐことが可能です。
債権譲渡登記には1件につき7,500円の登録免許税と司法書士への報酬が発生するので、合計で20,000円程度の費用がかかります。
なお、債権譲渡登記は法人対してしか行うことができないので、個人事業主がファクタリングを利用する際には債権譲渡登記の費用は必要ありません。
印紙代
ファクタリングの契約書には印紙税が発生するので、収入印紙代が必要です。
契約書に貼付する印紙代は契約金額に応じて次のように決められています。
- 1万円未満:非課税
- 1万円以上:200円
ファクタリングにおいて1万円未満の契約を締結することはありませんので、ファクタリング契約にかかる収入印紙代は200円であると理解しておけばよいでしょう。
振込手数料
ファクタリングによって買い取った売掛債権の代金を納入企業の口座へ振り込む際に発生する振込手数料です。
振込手数料を控除して代金を振り込むのが一般的ですが、ファクタリング会社によっては振込手数料を負担してくれる会社もあります。
詳しくはファクタリング会社へ確認しましょう。
交通費
ファクタリング会社の中には「契約時は面談が必須」となっている会社があります。
このような会社の中には、自社まで訪問してくれる場合があります。
この際の訪問にかかる交通費は基本的に納入企業が負担しなければなりません。
ファクタリング会社からの距離が通り場合には、交通費だけで数万円程度発生することもあるので注意しましょう。
ファクタリングの手数料を抑えるためのポイント

ファクタリングの手数料は、ファクタリング利用者が次のようなことに注意することによって抑えることが可能です。
- 複数業者から見積もりをとる
- 優良企業の売掛債権を売却する
- 金額の大きな売掛債権を売却する
- 信頼できるファクタリング会社と継続的に取引する
ファクタリングの手数料を抑えるための4つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
複数業者から見積もりをとる
ファクタリング契約の前には必ず複数の業者から見積もりを取るということを徹底してください。
手数料はファクタリング会社によってかなり異なりますし、ファクタリング会社と称する業者の中には法外な手数料を要求する悪質な業者も混じっている可能性があるためです。
何回かファクタリングを利用して、信頼できるファクタリング会社を見つけることができるまでは、基本的に複数の業者から見積もりをとって、手数料が安く対応のよい業者を探した上で契約締結するようにしてください。
優良企業の売掛債権を売却する
複数の売掛債権を保有しているのであれば、優良企業の売掛債権から先に売却することで手数料を低く抑えることが可能です。
ファクタリングの手数料は売掛先企業の信用によって左右されるので、未回収リスクの低い「上場企業・大手企業・業況良好な企業・官公庁」などの売掛債権は手数料が低くなる可能性があります。
手元に持っている売掛債権の中で、最も信頼できる売掛債権から先に売却するようにしてください。
金額の大きな売掛債権を売却する
手元に保有している売掛債権の中で、最も金額の大きな売掛債権を売却することでも手数料率は低くなります。
金額が大きくなれば、手数料の利率が低くてもファクタリング会社には十分な手数料収入が入るためです。
1つの売掛債権の金額が小さいのであれば、複数の売掛債権をまとめて1つのファクタリング会社へ売却することでも手数料を引き下げることができるでしょう。
信頼できるファクタリング会社と継続的に取引する
ファクタリングを利用する中で、信頼できるファクタリング会社が見つかったのであれば、継続的に取引することで手数料が下がる傾向にあります。
2社間ファクタリングの場合には、売掛先企業の信頼に加えて自社の信用も非常に重視されます。
取引当初は「この会社は期日通りに代金を支払う信頼できる会社か分からない」などと懸念されますが、取引を重ねるごとに信頼を蓄積していけば、ファクタリング会社にとってのリスクも低くなり、手数料も下がる可能性があります。
継続的に取引できるファクタリング会社を見つけることができたら、その会社と継続的に取引を行なっていきましょう。
ファクタリング手数料の注意点

ファクタリングの手数料に関係して、以下の3つの点には注意しなければなりません。
- 手数料以外の費用を要求する業者とは取引しない
- 20%を超える手数料が要求されたら他社の査定もとる
- 手数料が安くても「償還請求権あり」の業者とは取引しない
残念ながら、ファクタリング業者の中には違法な業者も混在しています。
そのような業者を避けて取引するためには、手数料に着目することが非常に重要になります。
ファクタリングの手数料についての3つの注意点について詳しく解説していきます。
手数料以外の費用を要求する業者とは取引しない
ファクタリングの手数料以外の費用を要求する業者とは取引しないようにしてください。
手数料には交通費や登記費用など、基本的に全ての費用が含まれています。
そのため、手数料とは別途、さまざまな名目でその他の費用を要求する業者は違法業者の可能性があります。
手数料以外にも費用を要求する業者とは基本的に取引しないようにしてください。
また、ファクタリングには消費税は発生しません。
消費税を要求する業者は根拠なしに顧客から多くの金額を要求しようとする業者の可能性があります。
このような業者とは取引しないように注意してください。
20%を超える手数料が要求されたら他社の査定もとる
2社間ファクタリングの手数料は10%〜20%程度が相場です。
そのため、20%を超えるような手数料が設定された場合には、法外な手数料を設定する違法業者の可能性が高いと考えた方がよいでしょう。
もちろん、売掛債権のリスクによっては20%を超えるような手数料を設定されるケースもあります。
しかし、20%を超える手数料が設定されたら「違法業者の可能性が高い」と判断し、他のファクタリング会社からも見積もりを取った方がよいでしょう。
手数料が安くても「償還請求権あり」の業者とは取引しない
「償還請求権ありのファクタリングにすれば、手数料を引き下げますよ」と提案するファクタリング会社も存在します。
「償還請求権あり」ということは万が一売掛債権が回収不能になっても、売掛債権の回収リスクを負わないということですので、手数料が安くて当然と言えば当然です。
しかし償還請求権ありのファクタリングは実質的には貸付と同じです。
貸付を行なっているにも関わらず貸金業者の登録を行なっていない業者は無登録の闇金業者となりますので取引をしてはなりません。
このような業者と取引してしまうと、ファクタリングと称して貸付を行なってきたり、執拗な取り立てが行われるリスクがあります。
ファクタリングは必ず償還請求権がない契約を締結するようにしてください。
ファクタリングの手数料相場についてのまとめ

ファクタリングにかかる手数料はファクタリングを利用する上で最大のデメリットと言えます。
特にファクタリングの手数料は暴利・ヤミ金と言われるほど高く、手数料の分だけ確実に経営収支が圧迫されてしまいます。
しかしながら、ファクタリングは融資とは異なり、比較的に素早い対応で資金調達をすることが可能です。
但し、手数料を不当に要求してくる悪徳業者だけには注意しなければいけません。
本記事で解説したファクタリングの手数料の相場や内訳を知れば、悪徳業者による不当な請求も見分けられるようになるでしょう。
個人でもご利用することができる現金調達サービスをご紹介いたします。
